『今さら勉強をするなんて、ちゃんちゃらおかしいわ!』
この【ちゃんちゃらおかしい】という言葉、あなたはちゃんと理解できていますか?
【ちゃんちゃらおかしい】という言葉には、ちょっと小バカにしているような、まるで鼻で笑うような態度がみえかくれしています。
今回は、この【ちゃんちゃらおかしい】という言葉の意味や語源、類語などを解説していきます!
『ちゃんちゃらおかしい』の意味
『ちゃんちゃらおかしい』の意味はつぎのとおりです。
(出典:大和ことば辞典)
『ちゃんちゃらおかしい』とは、あまりに馬鹿げていて、思わず笑ってしまうようなときに使う言葉です。嘲笑や冷笑の意味を込めて使うことが多い言葉です。
漢字で書くと、『茶茶羅可笑』となります。
『ちゃんちゃらおかしい』は、
日本固有の大和言葉で、どこか地方の方言ではありません。
このことについては、語源を知るとより理解できると思います。なので、つぎは語源について解説していきます!
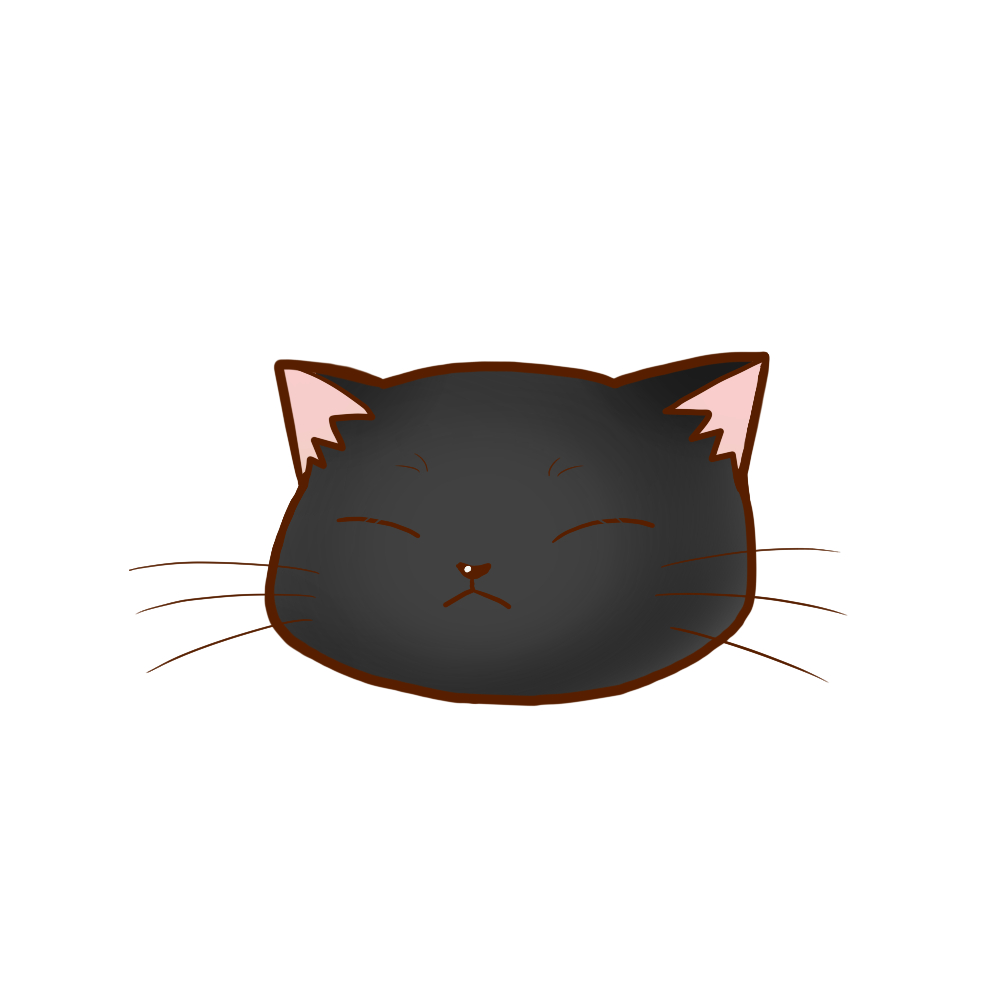
『ちゃんちゃらおかしい』の
❝ちゃんちゃら❞ってなんだろうにゃ?

つぎは『ちゃんちゃらおかしい』の
語源について解説するにゃ!
『ちゃんちゃらおかしい』の語源

『ちゃんちゃらおかしい』の語源について紹介します。
- 『ちゃんちゃら』とは、
【チャラ】を重ねてできたもの。
【チャラ】とは、口から出まかせを言うこと、またはそのような人のこと。 - 【チャラ】とは、【チャリ】が変化したもの。
【チャリ】という言葉は、茶ルの連用形⇒名詞に変化したもので、滑稽な言動をする者のことをいう。
(出典:語源辞典 形容詞編)
このように、『ちゃんちゃらおかしい』の
『ちゃんちゃら』とは、【チャラ】という言葉を重ねてできたものです。
そして、【チャラ】とは【チャリ】という言葉が変化したものです。
この【チャリ】という言葉ですが、
滑稽なことやおどけたことを意味します。
漢字では、【茶利】と書きます。
【茶利(チャリ)】⇒【チャラ】⇒
⇒【チャラチャラ】⇒【ちゃんちゃら】
つぎに、この【茶利(チャリ)】という言葉の語源は、つぎのとおりです。
滑稽なことという意味。
歌舞伎や浄瑠璃などでこっけい味を中心とした場面に用いる。『ちゃりば』という語の略称のこと。『ちゃりば』とは『阿闍梨場(あじゃりば)』が変化した言葉。
『阿闍梨場』とは、江戸時代中期、
大阪の豊竹座の並木宗輔作の浄瑠璃『和田合戦女舞鶴』での、豊竹河内太夫の愉快な語り口からできた言葉です。
『阿闍梨場』⇒『ちゃりば』⇒
⇒『ちゃり』へと変化した。
(出典:語源ものしり辞典)

このように、『ちゃんちゃらおかしい』という言葉は、【チャリ】という言葉から始まりました。
【チャリ】という言葉は、おどけたことや滑稽なことという意味があり、歌舞伎や浄瑠璃で登場する『阿闍梨場(あじゃりば)』という言葉が変化したものです。
『ちゃんちゃらおかしい』の使い方

こちらでは【ちゃんちゃらおかしい】の使い方について、例文をご紹介します。
例文1)
例文2)
例文3)
例文4)
『間抜け』という言葉の意味と、『馬鹿』との違いを解説しています!
>>『間抜け』とはどんな人?その語源や『馬鹿』との違いも解説します!
『ちゃんちゃらおかしい』類語・言い換え

つぎに『ちゃんちゃらおかしい』を別の言葉での言い換えや類語をご紹介します。
『ちゃんちゃらおかしい』という言葉は、次のように大きく2つの種類(要素)にわけることができます。
- 冷笑や嘲笑うようなさま
- くだらないさま
この2つの種類(要素)別に、それぞれ類語をご紹介します。
1.《冷笑や嘲笑うような様子をあらわす類語》
嘲る、嘲笑う、
鼻で笑う、ないがしろにする、
小ばかにする、ほくそ笑む、
コケにする
2.《くだらない様子をあらわす類語》
阿保臭い、阿保らしい、
馬鹿馬鹿しい、
こっけい至極、笑止の沙汰、
片腹痛い、ヘソが茶を沸かす
1番の『冷笑や嘲笑うような様子』には、あきれて冷めた感じの、少々見下すような態度があります。
2番の『くだらない様子』には、あきれてものも言えないような、思わず笑いが吹き出してしまうような、小ばかにしている態度があります。
『ちゃんちゃらおかしい』という言葉を別の言葉で言い換えるときには、文章全体が伝えようとしている雰囲気も掴むと、言葉選びがうまくできると思います。
※こちらの記事もおすすめ!
こちらの記事ではそのような感動の言葉をあつめました!
>>【感動】を言葉で伝えよう!心に響く感動の気持ちをあらわす言葉まとめ。
『ちゃんちゃらおかしい』を丁寧な言い方で

『ちゃんちゃらおかしい』をもう少し丁寧な言い方で表現する時には、つぎのような言葉があります。
軽蔑する、揶揄する、冷やかす、幻滅する
※こちらの記事もおすすめ!
まとめ
今回は『ちゃんちゃらおかしい』という言葉について、解説しました。
『ちゃんちゃらおかしい』の要点をまとめるとつぎのとおりです。
- 意味は、滑稽である、馬鹿馬鹿しくて笑ってしまうようなさまのこと。
- 漢字では『茶茶羅可笑』
- 方言ではなく、日本固有の大和言葉
- 語源は【茶利】。
これは浄瑠璃などの『阿闍梨場』という言葉が変化したもの
日本語って面白いですね!
最後までお読みいただきまして、ありがとうござました。



コメント
「大和言葉」って、飛鳥時代より前の言葉ってニュアンス強くないですか?
コメントありがとうございます^^大和言葉もさまざまですよね!聞いた話では、昔の言葉は、時代をさかのぼる程、英語やフランス語などの外国語より、はるかに聞き取れないそうです。まるで違う言語のように聞こえるそうです。